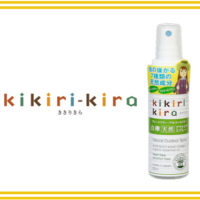- Home
- アタマがだいじ。カラダもだいじ。
- 夏に元気な「香味野菜」
コラム
8.292019
夏に元気な「香味野菜」

暑い日が続き「夏バテで体がだるくて食欲もない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
暑さで食欲もあまりないというときは、香味野菜をうまく取り入れて食欲を増し、残りの夏を体調良くすごしましょう。
茗荷も生姜も大葉も・・・。
香味野菜は爽やかな香りや、すっきりとした辛みで夏の食卓には欠かせない存在です。
香味野菜には食欲不振、疲労感、汗が出にくいといった症状を改善する働きがあります。
その他、香味野菜をうまく使うことにより、減塩にもつながります。
■生姜(しょうが)
栽培した年にできる「新しょうが」、栽培して2年以上の「ひねしょうが」があり、香り・辛味ともにひね生姜が強く、炒め物や薬味に使われます。
新生姜は、やわらかくてみずみずしく、甘酢等に漬けて食べられます。
生姜に含まれる成分「ジンゲロン」が血管を広げ、血行を促進するとともに発汗作用を促します。
とりわけ、冷え性の人には身体を温める効果が高いです。
ジンゲロンは胃液の分泌を促して、消化促進・食欲増進など、健胃にも役立つ成分です。
■紫蘇(しそ)
夏の食卓の名脇役ともいわれる、さわやかな香りと色で食欲を増進させてくれる紫蘇。
花・実・葉のいずれも薬味として使われています。
しその香りは、ガンやアレルギーを予防し動脈硬化を防ぐはたらきもあるとも言われています。
香りの成分のペリルアルデヒドには強い防腐作用があり、食中毒を防ぐ効果があると言われているので、刺身のつまとして最適です。
その他には整腸作用、風邪の予防、アトピーや花粉症にも効果があると言われています。
■セロリ
セロリはカロチンとビタミンCを多く含んでおり、カロチンは全身の代謝をよくし、ビタミンCはストレスに対する抵抗力をつけたり、健胃、血圧降下などの効果があります。
セロリの香りに含まれているセダノリッド、アイピンは口の中をサッパリさせる働きがあるので、油っこい料理や肉の付け合わせにぴったりです。
生で食べると食欲を増す作用もあります。
茎よりも葉の方に栄養成分を多く含むので、すべて食べると良いでしょう。
■韮(にら)
いくらつんでも伸びてくると言う生命力の強さから、精力野菜として食されています。
疲労回復、肩こりなどに良いとされているビタミンB1を多く含み、そのビタミンB1を体内に長くとどめ効力を持続させる硫化アリルが含まれているのでスタミナがつきます。
またビタミンAも豊富で夏バテしたとき、風邪をひいたときなど疲労回復剤の役割とともにからだを温める効果もあって、冷え性、神経痛の方や疲れやすい方にお勧めです。
■茗荷(みょうが)
メインの食材になることはあまりありませんが、薬味として使われることの多い茗荷。
味も香りもクセが強いので好き嫌いは分かれますが、夏を感じられる食材としてとても重宝されています。
茗荷には二種類あり、7月~8月にかけて収穫されるものを夏みょうが、9月~10月にかけて収穫されるものを秋みょうがといいます。
また、秋みょうがの茎が伸び、やわらかくなったものをみょうがだけといい、こちらは3月~5月にかけて収穫されます。
茗荷の成分は、ほとんどが水です。
それにより、水分補給と栄養補給を兼ねられるために、夏のものとされているようです。
水以外には、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、リン、ビタミンB群、Cなどを含んでいます。
また、みょうがの香り成分はアルファピネンといい、ひのきに含まれるものと同じです。
夏の、日本の、「香味野菜」。
お料理のレパートリーにもカラダにも上手く取り入れたいものです。