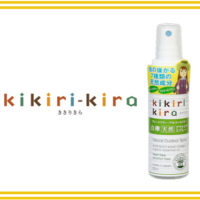- Home
- アタマがだいじ。カラダもだいじ。
- 朝型人間になれる人、なれない人
コラム
1.242019
朝型人間になれる人、なれない人

眠りの科学「睡眠学」については、脳科学と同様にここ数年で研究が飛躍的に進化しているようです。
と同時に、これまでの常識を覆すような新しい考え方が、たびたびメディアでも話題になっています。
今日は、朝に強い人間とそうでない人間は遺伝子による、というお話です。
ちなみに、国内外に早起き/早寝を称賛することわざは多く存在します。
「早起きは三文の徳」
“The early bird catches the worm.”
「早寝早起き病知らず」
“Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. “
逆に、早起きできない人はダメ!というレッテルが貼られがちです。
朝起きられないのは、スマホやパソコンの使い過ぎだとか、眠りが浅い、睡眠の質が悪いためだとか、よく言われています。
ところが最近、早起きができるか否かは遺伝子によって、決まっているという学説が浮上しています。
それによると、どうも人類全てが朝型人間にはならないようです。
私たちは睡眠サイクルをコントロールすることは実はできないとのこと。
つまり、生まれつき、朝に強い人もいれば、夜行性のような人がいるのだそうです。
朝型タイプか、夜型タイプかを決める要因は、遺伝子にあるというのがこの学説!
某研究で、タンザニア北部に暮らす狩猟民族の33人を、3週間に渡って調査した結果、分かったことは、周りの人が寝ている中で、最低でも1人は起きている(た)ということ。
さらに、個々によって就寝、起床時間は異なっていたということです。
この研究では、睡眠には環境が大きく影響を与えているということと、それぞれの好みのサイクルがあるということが証明されました。
その好みのサイクルこそが、遺伝子が大きく関わっていると考えられています。
前述のように、いかに早く起きるのが良いのかということを謳った諺や記事が多く、それはもちろん間違ってはいませんが、もしあなたが長い間早起きできない人間だとしても、自分を責める必要はありません。
寝しなや夜中にパソコンをいじっていて、朝起きられない(あるいは朝起きない)習慣が続いていたならば、それは朝起きることを遺伝子レベルで拒否反応を示しているのかもしれません。
私たちにはそれぞれクロノタイプ(生まれつき好みである睡眠スケジュール)があります。
だから、自分自身の体内時計をムリやり調整しない方が良いことも多いのです。
あなたの知人や大切な人でも、睡眠について悩む人がいたならば、遅く就寝して遅く起床することを寛大に許してあげましょう。
なぜなら、それがカラダの理にかなっている可能性があるのだから。
現代社会では、朝型人間は生産性が高いと評価されます。
ですが、起きていても脳が働いてないと感じるなら、満足がいくまで寝た方がましではないでしょうか。
この学説で言うならば遺伝子上、朝6時から活動できる人は限られています。
ですが、働いている以上どんなクロノタイプだとしても、朝の会議など、早く起きなければならない事態はあります。
少しでも楽に朝起きられるようにするには・・・
・数時間早くベッドに入って、体を落ち着かせる
・朝起きたときに動きやすいように、水分補給を寝る前にしておく
・自分のテンションが上がる曲を、アラームにセットする
・カーテンを閉めずに朝日を自然の目覚めに取り込む
「早寝早起き」は誰でもできることじゃない。
それは早起きしない遺伝子の問題かも、という言い訳を自説で持てば
少し楽に生きられるかも・・・!